LinuxでサーバやPCを「再起動」する際によく利用されるのがrebootコマンドです。トラブルやOSアップデート後など、運用管理の現場で必須になるコマンドなので、オプションや利用時の注意点もあわせて整理しておきましょう。
rebootコマンドの基本
- 構文text
reboot [オプション]※rootユーザー権限が必要。 - 主な特徴
- 原則「即時再起動」(ユーザーへの事前通知なし)
- オプションでシステム動作をカスタマイズ可能
- ユーザーやサービスへの通知・待機はシャットダウンコマンドとの差分
rebootコマンド 主なオプション一覧
| オプション | 長い形式 | 概要・使い方 |
|---|---|---|
| -f | –force | 強制的に再起動。サービス停止やアンマウントなどを行わない |
| -n | –no-sync | sync(ディスク書き出し)をせずに即時リブート(推奨されない) |
| -d | –no-wtmp | wtmpログ(再起動履歴)へ記録しない |
| -w | –wtmp-only | 再起動せずwtmpログへ記録のみ |
| -l | なし | システムログ(btmp)に記録しない |
| -q | なし | 実行中プロセスを停止せずただちにリブート |
rebootコマンドの使い分け・注意点
rebootは通知なしで即時再起動。作業ユーザーや進行中のサービスがあってもそのまま再起動される。reboot -fは更に強力で、異常時・フリーズ時などどうしても通常終了処理できない時のみ推奨。- 通常運用時はシステム整合性維持のため、通常のreboot、shutdown、systemctlの利用が望ましい。
- 再起動前は
syncコマンドでキャッシュの書き出しを推奨。
- rebootオプションによる記録抑制(-l, -d, -w)や即時(-q)は高度な運用/緊急時用。
shutdownコマンド・systemctlとの比較
| コマンド | 主な用途 | 通知・待機 | 時間/メッセージ指定 |
|---|---|---|---|
| reboot | 即時リブート | 事前通知なし | 不可 |
| shutdown -r | 計画的・通知付きリブート | ログインユーザーへ通知 | 指定可能 |
| systemctl reboot | systemdベースOSのリブート | 通知や待機はshutdown同等 | 不可 |
使用例
・今すぐ通常通り再起動
reboot・強制的に再起動(緊急時のみ)
reboot -f・指定時刻や分後に再起動(shutdown経由)
shutdown -r +10 # 10分後に再起動
shutdown -r 23:00 # 23時に再起動・systemdによる再起動
systemctl reboot運用上のベストプラクティス
- 通常はreboot単独でOK。
- ターミナルでrootでの誤操作防止・ログインユーザー有無を事前確認。
- 必須サービス・DBなどが稼働中の場合、
shutdown -rで通知するか運用手順に従う。 - 強制再起動(
-f)は最終手段。できる限り避ける。 - トラブル時のため「
syncの3連打→reboot」で確実な書き出しを推奨。
まとめ
- rebootコマンドはLinuxで最もシンプルかつ確実な再起動手段
- オプションによる個別挙動や緊急時の使い方も知っておく
- 大規模運用やリモートサーバ運用ではshutdownコマンドやsystemctlも活用
Linux運用時は再起動で発生しうるリスク・挙動を正しく理解し、状況に応じた使い分けを徹底しましょう。
Linuxについて学びたい人はこちらもチェック
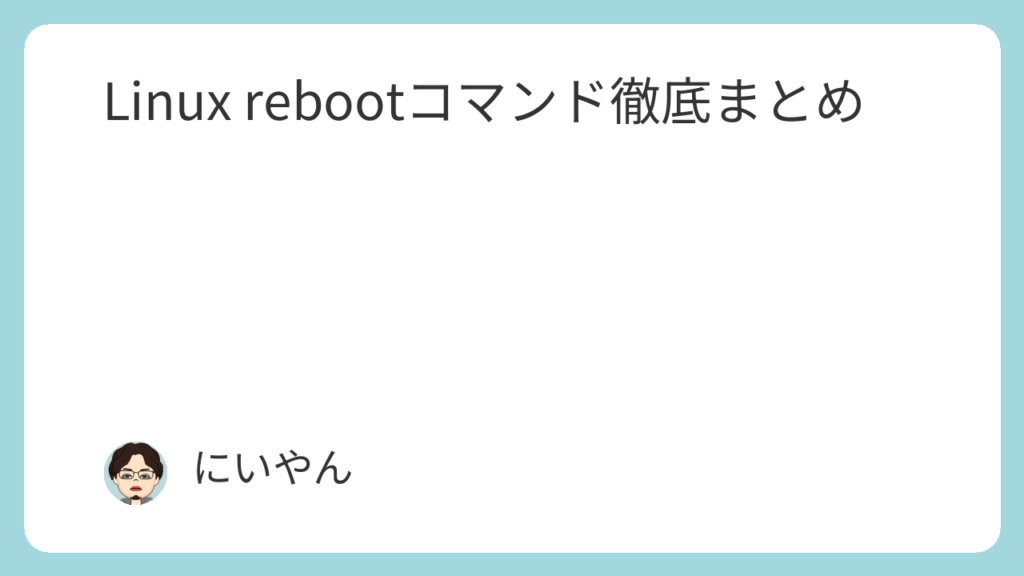
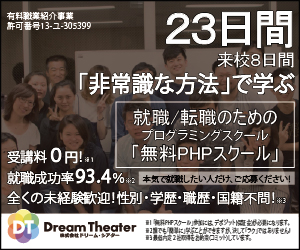



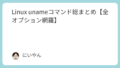
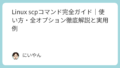
コメント